農協はその理念を十分に体現してきただろうか
信毎Webが社説で農協問題の記事を配信した。
このところ地方紙で協同組合問題を取り上げる記事はめっきり少なくなった。農協問題の重要さは強まっているときに「レイドロー報告」に基づいた指摘はお見事だ。
全文を掲載しました。御覧のほどを
信濃毎日新聞から
考ともに 農協の将来 誰のためであるべきか
下伊那郡松川町東部の山あい。生田地区の中心にある農協の建物は「地域のたまり場」だ。
日用品の売店があり、行政手続きや農協の金融関係の取り次ぎも受け付ける。一帯で唯一のガソリンスタンドもある。
みなみ信州農協(本所・飯田市)は、来年春で職員の常駐をやめると決めた。住民は事実上の撤退と受け止めている。
合理化は過疎・高齢化に合わせて進み、昭和50年代に30人ほど職員がいたのが、今は1人。
売店や行政の業務は現在、地域活性化を目的に住民が出資し合って設立した会社が受託する。農協撤退後、独自に続けるには、家賃など新たな負担が課題だ。
常駐廃止は生田地区だけではない。同農協は山間地を中心に管内の十数カ所を対象にした。
「農協が地域から離れていく」。住民出資会社の社長、下沢政弥さんは納得できぬまま「たまり場」存続の道を探っている。
国政では近年、安倍政権が農業と農協の「改革」を進めた。
政権復帰翌年の2013年に農業の「所得倍増」を掲げた。15年の農協法改正では組織の司令塔、全国中央会の権限を縮小させた。各農協の経営改善の自主性を阻害している、との理由だ。
環太平洋連携協定の大筋合意を受けた16年の「競争力強化プログラム」は、農協が提供する資材価格の引き下げが目玉になった。
論議は毎回、「攻め」の農業を強調する政府に、守旧派に位置付けられた農協側が押し込まれる構図が繰り返された。
当時の奥原正明農水事務次官は昨年出版した著書で、こう振り返っている。「(農協側に)改革を進めようとする人は全く見いだせなかった」
農協組織は戦後、「体制内圧力団体」と言われてきた。旧食管制度の代行機関として機能し、米価引き上げに傾注した。
そんな農協が零細な兼業農家を温存させ、効率化や規模拡大を妨げてきたとの批判は強い。
「脱農化」へ進んだとの指摘さえある。農家の農業収入が減っても会社勤めで貯金が増えれば信用(金融)事業にはプラスだ。6割の農協が本業の農業関連の事業は赤字で、信用と共済(保険)に経営を依存している。
競争力強化をアピールする政権が利用価値の減った圧力団体を見限った。専業農家の職能団体へ移行させる方へかじを切った。それが「改革」の内実であろう。
突きつけたのは、信用と共済事業の本体からの分離。そして今では正組合員を上回る人数になった「准組合員」の問題だ。農家ではなく農協のサービスを受けている人たちの利用制限である。
これらは農協の経営基盤に直結する。農協側は結局、いずれも検討の先送りに持ち込んだ。その上で、農産物の販売強化や資材供給の改善など「自己改革」に取り組むとした。従来の事業改善努力とどう違うのか。一般には分かりにくい当面の決着だった。
深まらなかった論点がある。そもそも農協は誰のためのものであるべきか、という問いだ。
政府方針に沿って零細農家から大規模農家に軸足を移すのか。地域住民を含めるのか。「みんなだ」と言い続けられるのか。
「協同組合の基本を踏まえぬ暴論」。政権の攻勢に、農協関係者からはそんな批判が目立った。
協同組合は資本主義の弊害を意識した存在だ。小さな存在が協力して市場原理に立ち向かう。
でも農協は、その理念を十分に体現してきただろうか。
戦時中の統制団体が前身にあり、戦後も行政の下請け機関としての性格が強かった。その延長に将来を描くことはできない。
関係者にはよく知られた問題提起がある。協同組合の運動家が1980年に出した「レイドロー報告」。指摘は今も通用する。
協同組合には社会と経済の両面の目的があるとし、社会的な使命に力点を置きつつ、経済性も軽視できない。必要なのは「常識的なバランス」と説く。
経済だけなら生田地区のような山間地からの撤退は当然かもしれない。だがそれを繰り返せば、農協の存在意義は足元から崩れていく。矛盾を内包し明確な解もない「バランス」をどうとるか。
規模は小さくても地域の動きに丁寧に目を配り、住民や自治体と協力して最低限守っていくべきラインを探る。そんな積み重ねを忘れてはいないか。自問してみることも必要だろう。
市場に任せればうまくいく。そう考える新自由主義は行き詰まりを見せている。農業と地域を支える協同組合があることの意義はむしろ、高まっているのだから。
(8月2日)
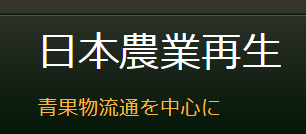

コメント